K-POPファンの間で大きな話題となっている「NewJeansのADOR復帰」と「謝罪論争」
「ILLITやルセラに謝罪しろ」という声がSNS上に溢れていますが、実際にNewJeansのメンバーが何か問題行動をしたのでしょうか?
本記事では、騒動の発端から報道の影響、ファン同士の対立構造までを整理しながら、“なぜNewJeansが批判の矢面に立たされたのか”をわかりやすく解説します。
また、K-POP業界の裏にある構造的な問題や、誤解が広まる仕組みも合わせて紹介します。
この記事でわかること
- NewJeans復帰をめぐる騒動の全体像と時系列
- 「謝罪論争」が起きた原因と誤解の正体
- ファン同士の対立がどのように拡大したか
- 今後K-POP界で同じ問題を起こさないための教訓
NewJeans復帰をめぐる騒動の経緯
2024年から2025年にかけて、NewJeansの活動をめぐるニュースはK-POP界全体を揺るがすほどの注目を集めました。ADORと親会社HYBEの対立、ファン同士の感情的な衝突、そしてネット上で飛び交う「謝罪しろ」という言葉——。それらは単なるアイドルのトラブルではなく、K-POP産業の構造やファン文化の問題をも浮き彫りにしました。
この章では、まず騒動の発端からNewJeans復帰に至るまでの流れを整理し、なぜここまで大きな論争になったのかを時系列でわかりやすく解説します。
ADORとHYBEの対立が始まったきっかけ
ADORは、NewJeansをプロデュースしたミン・ヒジン氏が代表を務めるレーベルで、もともとはHYBE傘下の子会社として設立されました。しかし、2024年春ごろから両者の関係に亀裂が入り始めます。発端は、ミン氏が「HYBEがADORの経営権を不当に奪おうとしている」と主張したことにありました。
これを受け、HYBE側は「ミン・ヒジン氏がNewJeansを独立させようとしている」と反論。両者の主張が真っ向から対立する形となり、訴訟や報道が連日続く状態になりました。
この時期、NewJeansのメンバーは立場を明確に示さず、静かに活動を続けていましたが、SNS上ではファン同士の意見が割れました。ADORを支持する声、HYBEを擁護する声、そして「どちらも悪い」と冷静に見る声までさまざまでした。こうした中で、グループの動向そのものが注目を浴び、わずかな発言や行動が拡大解釈されるようになっていきます。
「ILLITがNewJeansを真似ている」と言われた背景
対立の最中、HYBE傘下の別レーベル「BELIFT LAB」からデビューした新ガールズグループ「ILLIT」が登場しました。彼女たちのビジュアルコンセプトや楽曲スタイルがNewJeansに似ていると感じた人が多く、ネット上では「ILLITはNewJeansのコピーだ」という声が急増しました。
これに対し、ミン・ヒジン氏が「ILLITはNewJeansのコンセプトを模倣している」と発言したと報じられたことで、両グループのファン間での対立が一気に過熱します。
報道やSNS投稿の中には、ILLITやLE SSERAFIM(ルセラフィム)を直接批判するものもあり、次第に「ADOR(=NewJeans側)が他グループを攻撃している」との印象が広まりました。
実際には、NewJeansのメンバー自身が発言した事実は確認されておらず、ほとんどが外部のファンや一部メディアによる推測にすぎません。しかし、ネット上の空気は次第に「NewJeansが他グループを敵視している」という誤解を強めていったのです。
ネット上で生まれた“謝罪論争”の広がり
2025年秋、NewJeansがADORへの復帰を発表すると、SNS上には「おかえり」という祝福の声とともに、「ILLITとルセラに謝罪しろ」という厳しいコメントが多数投稿されました。この“謝罪論争”は、メンバー個人の行動に起因するものではなく、過去にミン・ヒジン氏が発した発言や、ファンコミュニティで生じた攻撃的なコメントが原因です。
特に韓国や日本のSNSでは、誰が悪いのかを明確にしようとする傾向が強く、「NewJeansの所属レーベル=ADOR=ミン・ヒジン」という図式で一括りにされることが多いです。そのため、実際には関与していないNewJeansのメンバーにも矛先が向かい、「謝罪しろ」という声が生まれたのです。
誤解や感情的な批判が拡散し、本来は運営間の問題であった対立が、グループ同士の争いのように見えてしまったことが、今回の論争の大きな特徴といえます。
なぜNewJeansに「謝罪しろ」と言われるのか
NewJeansのADOR復帰が報じられた際、SNS上では多くの祝福コメントと同時に「ILLITとルセラに謝罪すべき」という批判的な意見も見られました。この背景には、メンバー個人の行動よりも、メディア報道・ファンの対立構造・そして誤解の積み重ねが関係しています。
誤解の根源:ミン・ヒジン氏の発言と報道の影響
今回の論争の発端は、ADOR代表であるミン・ヒジン氏の発言に関する報道が大きく影響しています。2024年春頃、ミン氏が「ILLITがNewJeansのコンセプトを模倣している」と発言したという内容が各メディアに広まりました。
この報道をきっかけに、HYBE内のグループ同士が対立しているというイメージが作られ、ネット上では“ADOR vs HYBE”という構図が定着しました。
問題は、その報道内容が部分的に切り取られたものであったことです。ミン氏の発言意図は「NewJeansの独自性を守りたい」というものでしたが、一部のメディアがセンセーショナルに伝えたため、ファンや一般層の間で「ADOR(=NewJeans側)が攻撃した」という印象が拡散されました。
その結果、NewJeansメンバーが直接発言していないにもかかわらず、誤解が膨らみ「謝罪すべき」との声が増えていったのです。
ファン同士の対立が炎上を拡大させた経緯
K-POP界では、アーティスト本人よりもファンコミュニティの行動が問題視されるケースが多くあります。今回も例外ではなく、ILLITのデビュー後、一部のNewJeansファンがSNS上でILLITやルセラを攻撃するようなコメントを投稿し、炎上を拡大させました。
もちろんこれは全ファンの意見ではなく、過激な一部による行動でしたが、目立つ投稿ほど拡散されやすく、「NewJeansファン=攻撃的」という印象を強めてしまいました。
また、ファン同士の対立は感情的な面も強く、どちらの側にも“正義感”が存在します。ILLITのファンからは「NewJeansが被害者面をしている」、NewJeansのファンからは「ILLITがコンセプトを盗んだ」といった声が飛び交い、互いに譲らないまま炎上構造が固定化しました。
メンバー個人には非がないとされる理由
重要なのは、NewJeansのメンバー個人がこの論争に直接的な発言や行動を取っていないという点です。
彼女たちはあくまでアーティストとして活動を続けており、所属事務所やメディアが発信した内容に関してコメントしたことはほとんどありません。そのため、専門家やK-POPメディアの多くは「NewJeansメンバー自身に非はない」と分析しています。
誤解を解くために知っておくべきポイント
今回のNewJeans復帰をめぐる「謝罪論争」は、単なるK-POPファン同士のいざこざではなく、韓国エンタメ業界全体の構造的な問題を映し出していると言えます。メディアの報じ方、ファン文化の拡散力、そして企業間の力関係。これらが複雑に絡み合った結果、アーティスト本人たちが意図せぬ形で批判の的になってしまいました。
K-POP界で再び起きないための教訓
今回の一連の出来事から得られる教訓は、「情報の出所を見極め、感情的に反応しない」ことの重要性です。SNSの時代では、誰でも意見を拡散できる一方で、誤解や偏った情報が瞬時に広がるリスクがあります。
ファン文化をより健全に保つためには、「本人の行動」と「運営・ファンの行動」を明確に区別することが欠かせません。
まとめ
- NewJeansのADOR復帰はHYBEとの契約問題の決着によるもの
- 「謝罪論争」はメンバー個人の行動ではなく誤解から生まれた
- 発端はADOR代表ミン・ヒジン氏の発言に関する報道
- ILLITやLE SSERAFIMとの「模倣疑惑」がSNSで拡散された
- ファン同士の対立が炎上を拡大させた最大の要因
- メンバーは沈黙を守っており、直接的な非は確認されていない
- SNSやメディアの情報が一部切り取られて誤解を生んだ
- 運営間のトラブルがアーティストにまで波及した構図
- 今後の課題は、ファンコミュニティの健全化と冷静な情報判断
- NewJeans・ILLIT・ルセラは本来“競争”より“共存”を目指す存在
今回の騒動を通じて浮かび上がったのは、情報の錯綜と感情的な拡散がもたらす危うさです。NewJeansのメンバー自身は騒動に直接関与しておらず、むしろ渦中で静かに音楽活動を続けてきました。
誤解を解く鍵は、誰かを一方的に責めることではなく、状況を多角的に理解しようとする姿勢にあります。
そして、K-POPという巨大なカルチャーを支えるのは、アーティストだけでなくファンやメディアの責任ある行動でもあることを、改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。

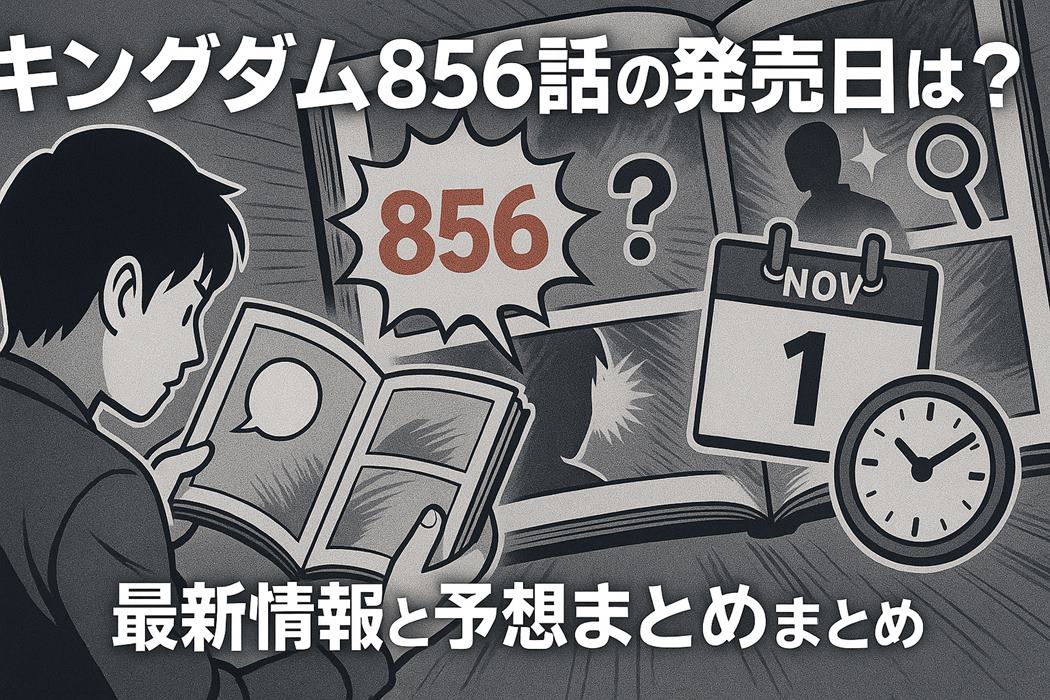
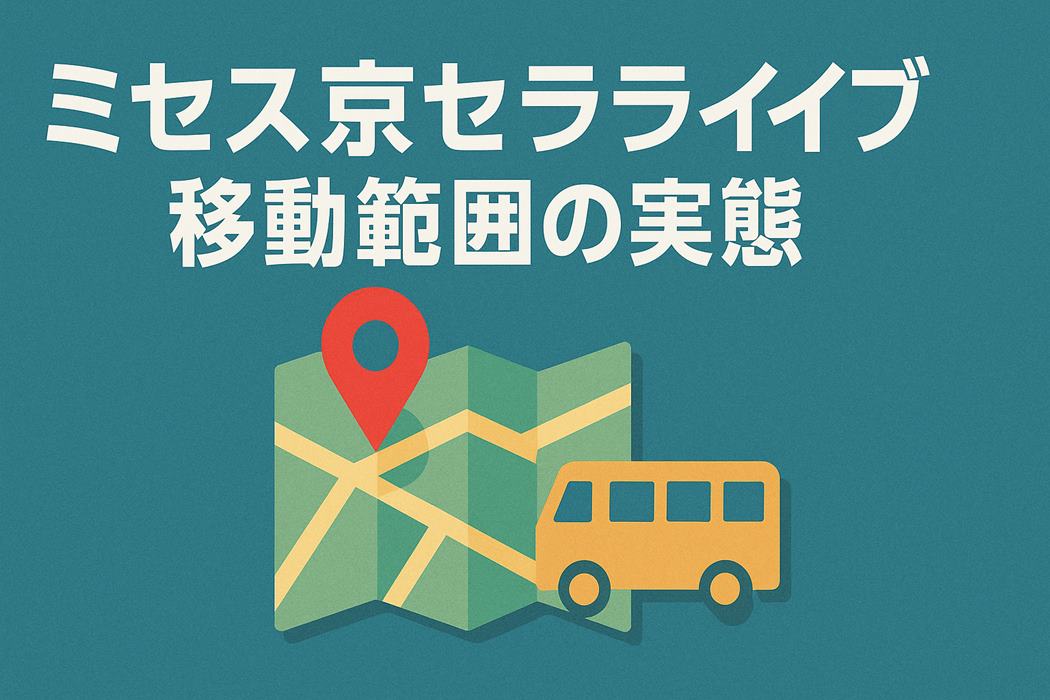
コメント